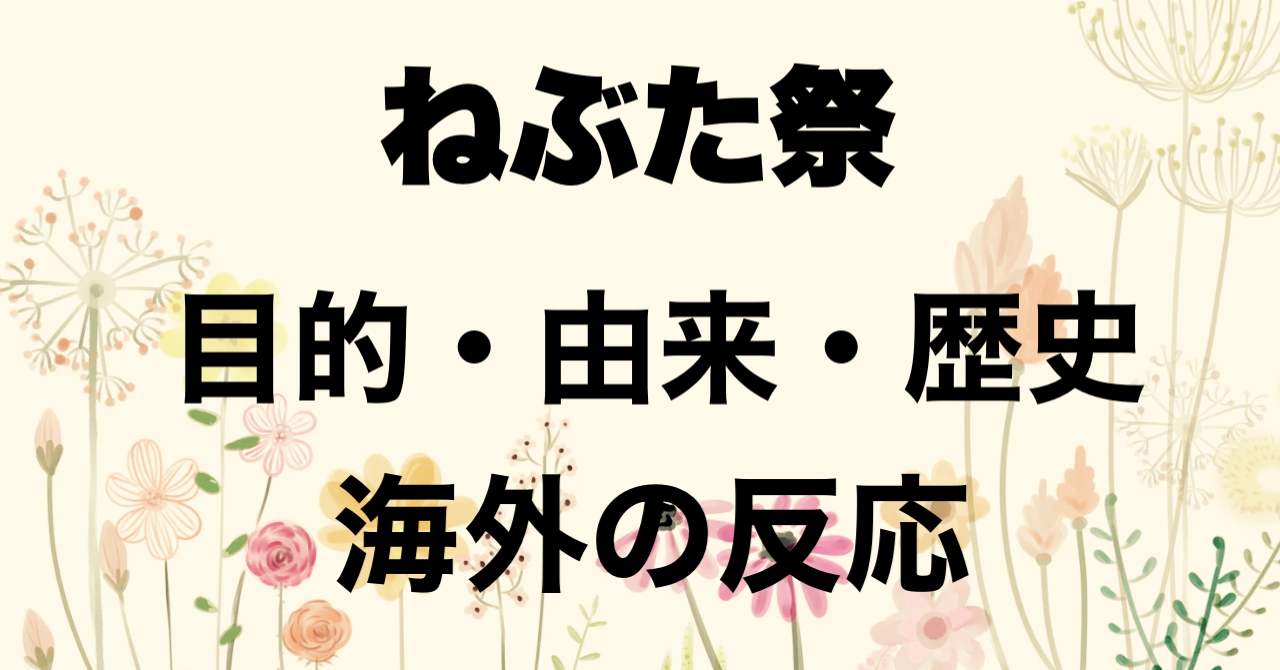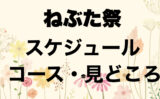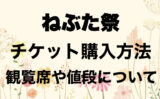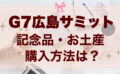東北三大祭りとして全国的に有名な青森ねぶた祭。近隣の人々だけではなく、日本全国からツアーや個人で訪れたり、海外から訪れる外国人もいるほどの人気ぶりです。そこで今回は、2023年の青森ねぶた祭の概要についてや、ねぶた祭の目的、由来、歴史や海外の反応についても調べてみました。
青森ねぶた祭の概要
青森ねぶた祭とは
青森ねぶた祭りは、青森県青森市で毎年開催される夏祭り(日本の火祭り)で、仙台七夕まつり、秋田竿燈まつりと並ぶ東北三大祭りの一つです。
1980年(昭和55年)には、国の重要無形民俗文化財に指定されています。
毎年、延べ約270万人以上の観光客が日本全国や海外からも訪れます。
伝説や歴史上の人物、歌舞伎、神話を題材に制作された「ねぶた」や、その周りで鈴をならしながら掛け声で踊っている「ハネト」、笛や太鼓など壮大なスケールでお祭りが行われます
日程・時間
青森ねぶた祭の開催日は、毎年曜日に関係なく同日に行われます。
日程:2023年8月2日(水)~7日(月)
8月1日:前夜祭(18:00~21:00) ねぶたの運行はありません。
8月2~3日(19:00~21:00):地域の子供たちによる「子どもねぶた」10台予定、大人たちによる「大型ねぶた」15台予定が運行します。
8月4~6日(18:50~21:00):祭りが一番盛り上がりを見せる3日間です。大型ねぶたが20台運行します。
8月7日(13:00~15:00):大型ねぶた20台がこの日だけ昼間に運行します。そして、19:15~20:45まで、青森港でねぶたを船に乗せて周遊する海上運行と花火大会が行われ、ねぶたと花火大会を同時に楽しむことができます。
青森ねぶた祭の目的は?
由来・歴史・願い
青森ねぶた祭の起源は定かではありませんが、おそらく七夕祭りの灯籠流しの変形であろうといわれています。
奈良時代に中国から渡来した七夕祭と、古くから津軽にあった習俗と行事が合わさって灯籠となり、それが変化して現在のねぶたになったと考えられています。
7月7日の七夕祭では、「けがれ」を川や海に流す「みそぎ」として「ねぶた(灯籠)」を流し、無病息災を祈りました。
この「ねぶた流し」が、現在の青森ねぶたの海上運行となっています。
観光客数について
観光客数は毎年増減はありますが、おおよそ全日程を通し、延べ280万人以上の人々が訪れます。
ただ2022年は新型コロナウイルスの影響で3年ぶりの開催となり、延べ人数は105万人と激減しています。
2019年(前回)は285万人であったことから、観光客が約6割も減少しています。
2023年は、旅行会社のツアーもキャンセル待ちが出るほどなので、観光客数も回復しつつあるのではないでしょうか。
海外の反応
海外からの観光客による青森ねぶた祭への反応です。
- 浮世絵みたいで美しい
- 外国人も参加できるならやってみたい。
- この祭りには是非参加したい。
- 海に浮かぶねぶたと花火が素敵!
- 正直かっこいい!
- 雨が降ったらどうなるの?
- みんなに知ってほしいからシェアしよう。
- 本当に迫力がすごい。一度は観に行くべき。
- 印象的で風土的だ。

どれも的を得た反応ですね!
次回は参加できるといいですね。
まとめ
今回は、青森ねぶた祭の由来や歴史等についてや、訪れた外国人にはねぶた祭をどのように映っているのかの海外の反応についてもまとめてみました。
由来や歴史については、「~であろう」という形で、定かではないですが、現在に至るまでの歴史については理解できるかと思います。
無病息災を願うお祭りですが、奈良時代に灯籠だったものが現在のねぶたに変化し、七夕祭がねぶた祭となってフィナーレに海上運行をすることで継承されています。
海外の反応では、ねぶたの美しさに感動する外国人の意見が多いですが、外国人だけではなく日本人も一度は観たいお祭りのひとつではないでしょうか。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
\国内ツアーで探すならこちら/
\個人旅行で探すならこちら/